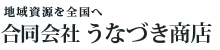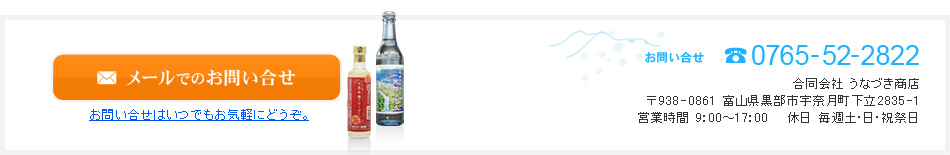富山県魚津市加積産 加積りんごの歴史
「完熟林檎のサイダー」のキーワード、それは「100年」。
「完熟林檎のサイダー」に使用されている天然伏流水は、約100年の歳月をかけ北アルプスから黒部川大扇状地の地中を流れ磨かれて、日本海に面する生地地区に清水(しょうず)となり、地表に湧き出てきます。まさに人の手が一切入らない、大自然の力のみで長い時間(とき)をかけて磨かれた、贅沢な水なのです。
そして、もうひとつの100年。
それは、1905年(明治38年)から栽培が開始された、加積(かづみ)りんご。
ブランド果樹としての地位を確立するまでの道のりは、苦難の歴史でもありました。
栽培開始から戦前までは病害虫の発生に苦しみ、戦中は強制伐採など困難な時代を経てきました。戦後は藻の不足から、りんごが大変貴重品扱いされた時代もありましたが、昭和30年代は災害の連続で、栽培面積の増加にもかかわらず収穫はほとんど伸びない大変苦しい時代でした。1960年(昭和35年)の雪害では、樹木が文字通り「生木を裂く」の状態になりました。その傷も癒えぬ1961年(昭和36年)には大型台風の来襲。大量の落果が畑を埋め尽くしたのです。1964年(昭和39年)の降雹、翌1965年(昭和40年)の大型台風と災害は続きました。その後も度重なる災害に直面するも、生産者一丸となって、りんご生産地存亡の危機を乗り越えてきたのです。

加積りんごを支える生産者の「想い」
全国的には小規模な産地にもかかわらず、高品質で大変美味しいりんごの安定生産を実現している大きな要因の一つが、強固な共同体制を確立している点です。 その中でも「加積りんご研究会」が発足された1951年(昭和26年)以降は、加積りんごのブランド化の先駆けとなりました。
1949年(昭和24年)から2年余り、当時りんご栽培先進地であった青森への現地視察を重ね、1951年(昭和26年)10月にりんご栽培への熱い「想い」を抱く栽培者9名により「加積りんご研究会」が発足。その後も会員は増加し、先人の「想い」を受け継いで、 日々栽培技術の研究に努めています。また、「加積りんご研究会」では、毎年講師を招いての技術研修会を開催すると共に、先進地への視察、剪定、摘果仕上がり、ふじ仕上がりの各畑回りを行い、生産者間の栽培技術向上を進めています。

加積りんごを支える「匠」の技術
かつて、「りんごの鬼」と言われ、「りんご道」と自らが語る果樹栽培技術を確立した「ふじ」の育ての父である、青森県のりんご栽培農家「斉藤昌美」氏は、りんご栽培についてこう語っています。
「伸びる枝を伸ばさず、伸びない枝を伸ばすのが剪定の哲学である。骨は仁王のごとく、成り枝は蛇のごとく、枝に翼をつけると良いりんごが飛んでくる」
「りんごの樹は、枝の一本一本、葉の一枚一枚のならせ方で、全く違う果実を実らせるんだ。樹の生命力をコントロールし、理想の果実を実らせる剪定は、りんごづくりの命なんだ」
(引用先:プロジェクトX 新・リーダーたちの言葉)
加積りんごの栽培における「剪定」作業は、雪が降りしきる1月から開始されます。実はこの「剪定」次第で、りんごの味が大きく変わると言われているのです。しかも、りんごの樹は人と同じ生き物。剪定すべき枝は、枝の張り方・方角・土壌によっても異なり、また2年後3年後に切る枝も考え、樹と対話しながら行われます。それらの技術は、100年に及ぶ加積りんごの歴史の集大成でもあるのです。